就活スケジュールの「滞り」をなくす——『はかどる技術』に学ぶ効率アップの極意
頑張っているのに進まない理由
就活生からよく聞く悩みのひとつに、
「毎日予定を詰め込んでいるのに、なぜか成果が出ない」というものがあります。
- 朝早く起きてESを書き、昼は企業説明会、夜は面接対策。
- 気づけば一日中動いているのに、やり残しが山積み。
- やる気はあるのに、スケジュールが破綻して自己嫌悪——。
私も学生時代、そうでした。
「時間を埋める=効率化」だと信じていたのです。
そんな常識を覆してくれるのが、鈴木邦成さんの『はかどる技術』。
物流のプロが語る「滞り」の発想
著者の鈴木邦成さんは、物流エコノミストであり、日本大学教授。
現場でモノの流れを最適化してきた経験から、「仕事の効率化は滞りをなくすこと」だと断言します。
「滞り」とは、流れを妨げるピークのこと。
朝や月曜の午前中など、タスクや情報が集中する時間帯に無理に重要なことを入れると、効率はかえって落ちる——これは就活スケジュールにも当てはまります。
就活あるある「ピークの罠」
例えば、多くの学生が「朝活でESを書く」と決めます。
でも朝はメールチェック、授業準備、身支度、移動…とピークが重なる時間帯。
そこに集中作業を押し込むと、慌ただしさに飲まれて質が下がります。
また、月曜朝に自己分析や新しい志望動機作りを始めるのも危険です。
週明けは急な予定変更や企業からの連絡が入りやすく、集中を奪われがちです。
学生Aのエピソード:朝活疲れからの脱却
Aさん(文系4年)は、「朝は脳が冴えている」との本を信じ、毎朝6時に起きてES作成をしていました。
しかし結局、通学準備や連絡対応に追われ、集中できたのは30分程度。
夜は疲れ果てて寝落ちの日々。
本書の「ピークを避け、昼の2時間に集中する」という提案を試したところ、授業の空きコマをES作成に充てられるように。カフェや図書館で落ち着いて書けるため、作業効率が2倍に上がりました。
会議は金曜夕方、就活は…?
著者は、会社の会議は金曜夕方がベストと説きます。理由は、週明けの慌ただしさを避け、週末前の落ち着いた時間に意思決定できるからです。
就活でも同じです。
面接やOB訪問は、可能であれば週半ば〜金曜に設定する方が、相手も自分も落ち着いて臨めます。月曜朝イチや週明けすぐは避けるのが賢明です。
前倒しすぎも非効率
本書では、締め切り前に無理に前倒しすることの弊害も指摘しています。
例えば、金曜締め切りの課題を月曜に仕上げても、その後の情報更新や方向転換で手直しが必要になるかもしれません。
就活でも、ESを出す直前に企業の最新ニュースや説明会で得た情報を反映した方が、説得力が増します。「早ければ良い」ではなく「最適なタイミングで出す」。これが重要です。
隙間時間のモジュール化
物流現場には「3定(定位・定品・定量)」という整理の基本があります。
本書はこれを時間管理にも応用し、「隙間時間のモジュール化」を提案しています。
- 5分空いたら:メール返信
- 10分空いたら:自己分析のメモ
- 20分空いたら:企業研究の要約
こうしておくと、予定と予定の間の「スキマ」が生きた時間に変わります。
学生Bのエピソード:移動時間が宝の山に
Bさん(理系3年)は、研究室と企業説明会の移動で1日2時間以上を電車で過ごしていました。
これまでスマホゲームで消費していた時間を、「モジュール化」したタスクに置き換えたところ、1週間でESの下書き3本分を完成させられるようになりました。
仕事とプライベートを切り替えない?
意外なのが、「仕事とプライベートを切り替えるな」という著者の主張。
就活でいえば、自己分析や企業研究を完全に“就活時間”に閉じ込めず、日常の会話や趣味の中でも自然に考える、ということです。
例えば、映画を観ながら「この監督の企画力は、マーケ職の発想に似ているな」と気づく。こうした日常とのシームレスなつながりが、志望動機や面接での話に深みを出します。
まとめ—「滞り」をなくせば就活ははかどる
『はかどる技術』の本質は、「予定を埋めることが効率化ではない」という逆転の発想です。
- ピークを避け、落ち着いた時間に集中する
- 前倒ししすぎず、最適なタイミングを見極める
- 隙間時間をモジュール化する
- プライベートも就活に活かす
これらを取り入れるだけで、就活の進み方は大きく変わります。
やる気や根性より、「流れを整える工夫」。これこそが、就活を「はかどらせる」最短ルートです。
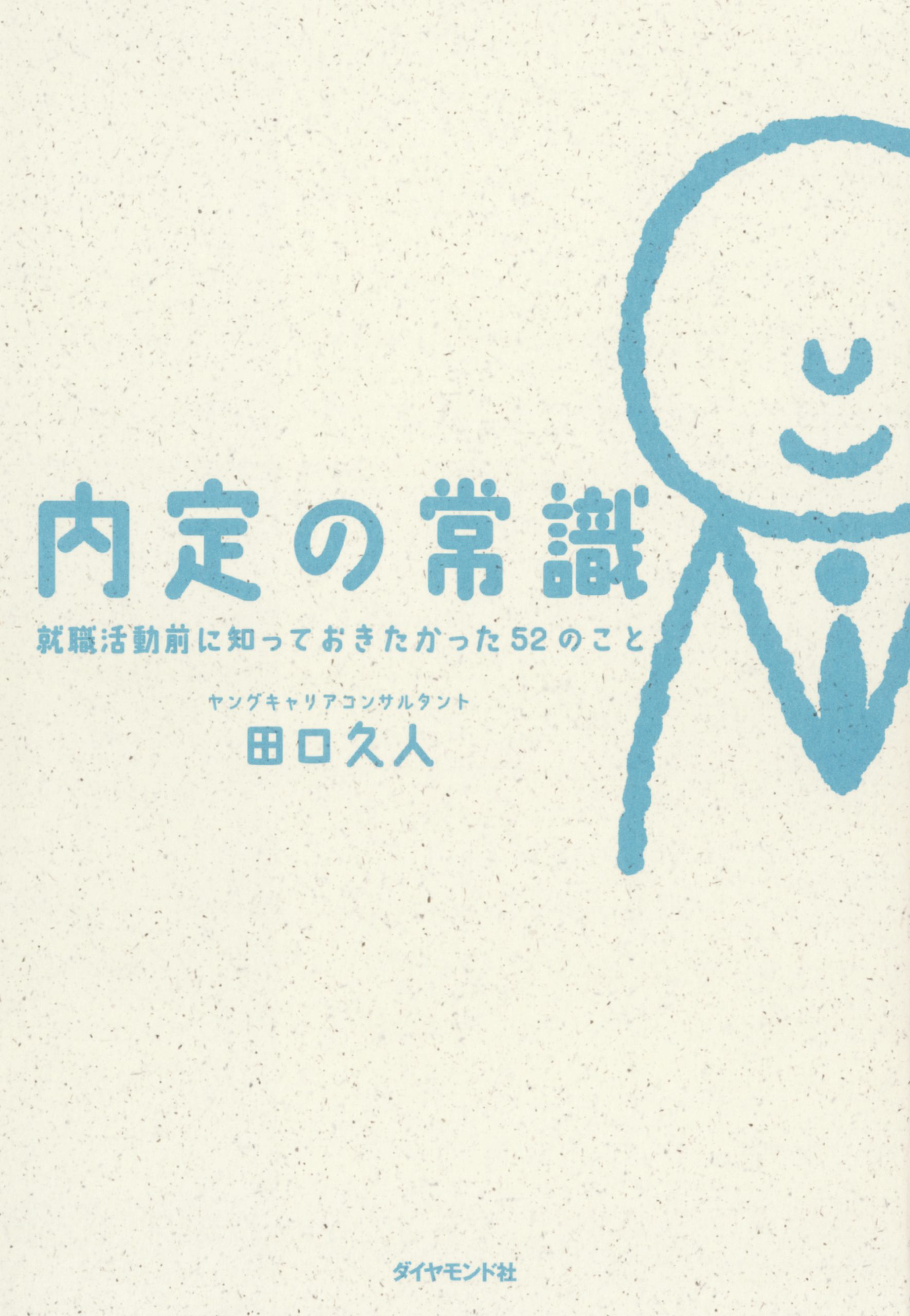
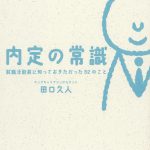
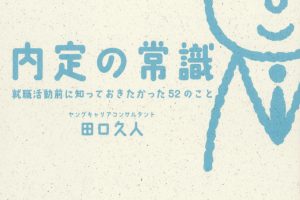
-300x200.jpg)





