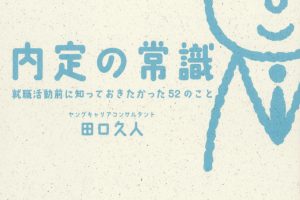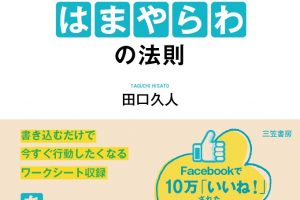就活の不安を乗り越える「理性の筋トレ」——『STOIC 人生の教科書ストイシズム』が教える90日間
不安に押しつぶされそうになる夜
就活が本格化してくると、夜ベッドに入っても眠れない日が増えます。
「今日の面接、あの答えでよかったのかな」
「また不採用のメールが来たらどうしよう」
「そもそも自分は何がやりたいんだろう」
そんな思考が頭の中でぐるぐる回り、目が冴えてしまう。
友達の内定報告がSNSに流れてくると、胸が締めつけられる。
——この精神的なプレッシャーに、どう立ち向かえばいいのか。
そんな人におすすめなのが、ブリタニー・ポラット著『STOIC 人生の教科書ストイシズム』。
ストイシズムは「理性を鍛える哲学」
ストイシズム(ストア哲学)は、古代ローマで栄えた実践哲学です。
セネカ、エピクテトス、マルクス・アウレリウスといった哲人たちが説いた教えは、シリコンバレーの起業家や世界のビジネスリーダーにも支持されています。
本書は、そのエッセンスを90日間の実践プログラムに落とし込みました。
1日見開き2ページ構成で、右に哲人の名言、左に実践ワーク。
読むだけではなく、書き込み、考え、日々の行動に落とし込む設計になっています。
就活でこそ必要な「4つの美徳」
ストイシズムには「4つの美徳」があります。これは就活にも直結します。
- 知恵:うわべに惑わされず、本質を見抜く力
- 正義:他人に思いやりを持ち、公正に接する力
- 勇気:苦難や不安に立ち向かう力
- 節制:衝動や焦りを抑える力
面接での緊張、ESでの自己否定、周囲との比較。
こうした感情に飲まれず、自分の判断を理性で導く——これこそがストイックな生き方です。
学生Aのエピソード:不採用続きからの回復
文学部のAさんは、秋の時点で10社連続不採用。
「自分には価値がないのでは」と自己否定のループに陥っていました。
本書のワークで出会ったのが、マルクス・アウレリウスの言葉。
「もしそれが正しくないことであれば、するな。事実でないことであれば、口にするな。」
Aさんは、この一文をスマホの待ち受けに設定。
自己否定の言葉を口にしそうになったら、この言葉でストップをかけました。
結果、感情に振り回されず、次の面接に集中できるようになったのです。
「刺激」と「反応」を切り離す
ストイシズムの重要な考え方に、「刺激」と「反応」は別であるというものがあります。
たとえば、面接官に厳しい質問をされたとき。
多くの人は「批判された」と反射的に感じ、焦ってしまいます。
しかし、質問は単なる刺激であり、それにどう反応するかは自分次第です。
この視点を持つと、就活での予想外の出来事にも落ち着いて対応できるようになります。
学生Bのエピソード:圧迫面接を乗り切る
経営学部のBさんは、ある面接で圧迫気味の質問を受けました。
「うちの仕事、君には向かないんじゃない?」
以前なら動揺して沈黙してしまう場面です。
しかしBさんは、本書で学んだ「刺激と反応は別」という原則を思い出し、こう切り返しました。
「向かないとお感じになった理由をお聞かせいただけますか。その上で私の強みと照らし合わせたいと思います。」
結果、その場が建設的な対話に変わり、内定を獲得しました。
「知っている」を手放す勇気
エピクテトスはこう言います。
「自分は知っているという考えを捨て去れ。
人は知っていると思っていることについて学ぼうとはしない。」
就活で失敗が続くと、「自分はやり方を知っているはず」という慢心や、逆に「自分はダメだ」という思い込みに縛られます。どちらも成長を止めてしまう心のクセです。
「知っている」を手放し、常に学び続ける姿勢こそ、長期的な成長のカギです。
目に見えない資質を数える
本書にはこんなワークもあります。
「自分にあってよかったと思う、目に見えない資質を10個リストアップする」
就活では、目に見える成果(資格、経験、成績)ばかりに意識が向きがちです。しかし、誠実さ、粘り強さ、協調性など、目に見えない資質こそ長期的に評価される力です。
喪失を恐れない
ストイシズムは「すべてはかりそめ」と受け入れることで、喪失の恐れから自由になります。
就活で言えば、「落ちること」や「逃したチャンス」に過剰に執着しないこと。
次の機会が必ずあると信じ、今やるべきことに集中する。
その落ち着きが、結果的に良いご縁を引き寄せます。
まとめ——就活は理性を鍛える最高の舞台
就活は、自分の価値観や信条を試される連続です。ストイシズムの4つの美徳は、その中で理性を鍛え、不安や焦りをコントロールする力を与えてくれます。
『STOIC 人生の教科書ストイシズム』の90日プログラムは、就活だけでなく、その先の人生を支える「心の筋トレ」です。
もし今、不安や焦りで押しつぶされそうなら——この90日間を、あなたの未来への投資にしてみてください。
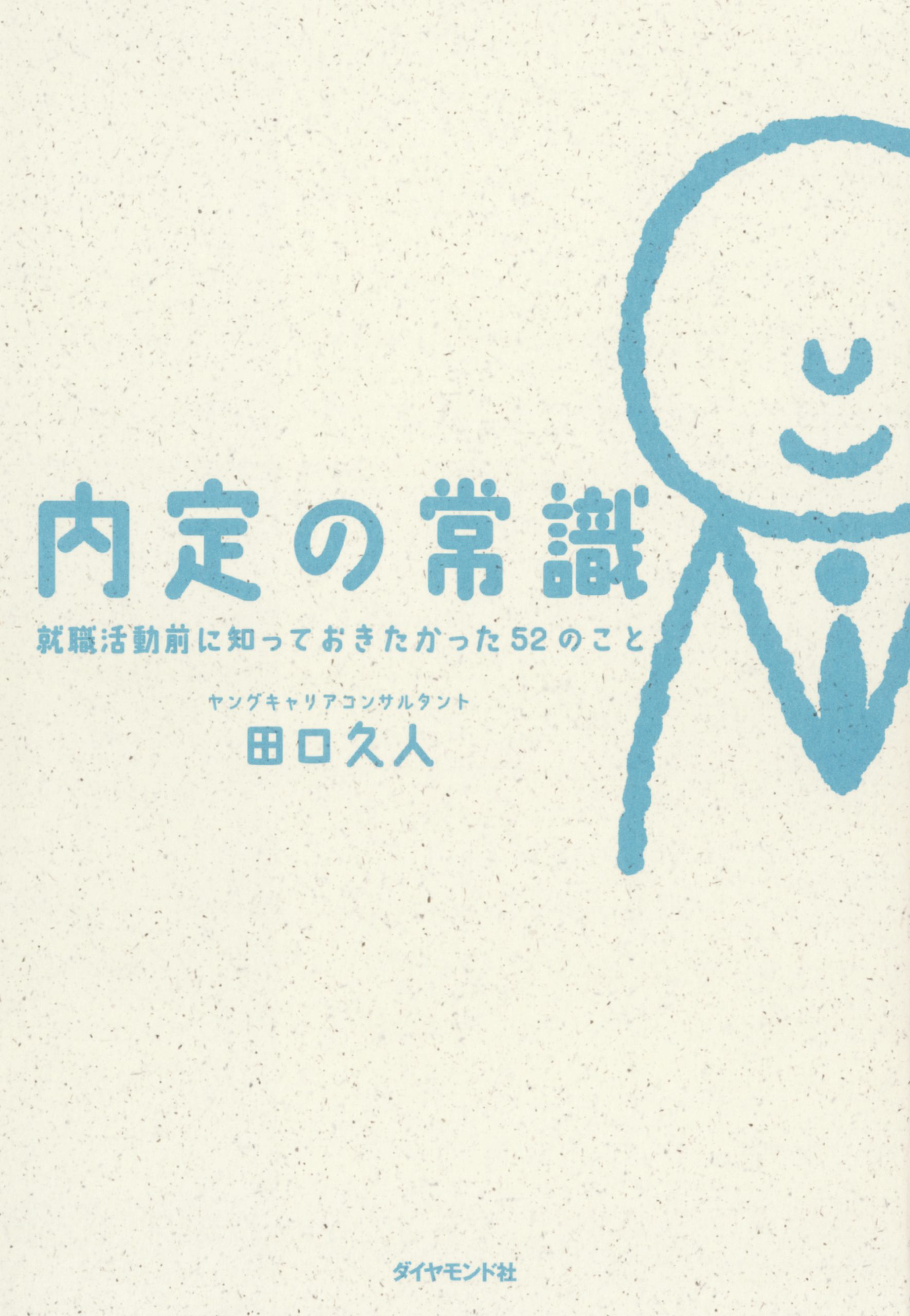
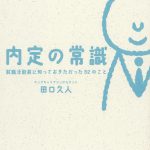
-150x150.jpg)