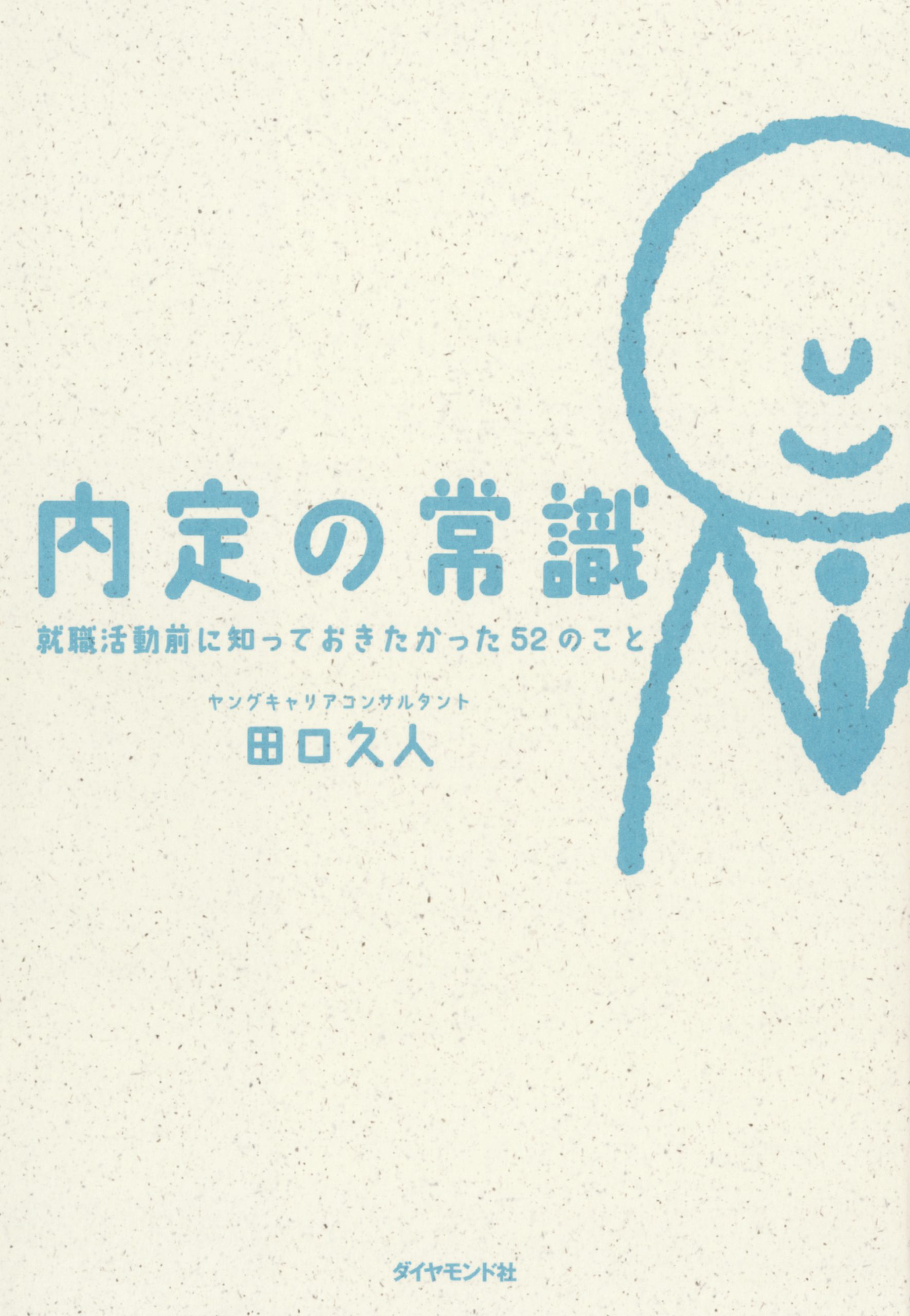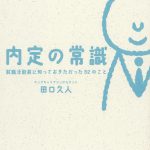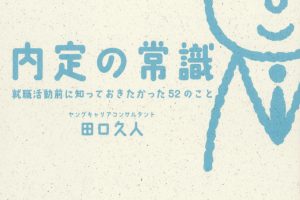就活生のための「ビジネスの地図」——『13歳からのMBA』で学ぶ社会と仕事の基本
就活準備で気づく「社会のこと、意外と知らない」感覚
就職活動を始めると、多くの学生がある壁にぶつかります。
それは——「社会やビジネスの仕組みを意外と知らない」という事実です。
- 面接で「当社のビジネスモデルをどう考えますか?」と聞かれて固まる
- グループディスカッションで利益やコストの話になると、急に発言が減る
- 「お金の流れ」を理解していないため、志望動機がふわっとしてしまう
そんな人におすすめなのが、中川功一さんの『13歳からのMBA』です。
13歳でもわかる、でも奥が深い
著者の中川功一さんは、東京大学経済学博士であり、やさしいビジネススクール学長。
この本は、経営学の基礎を「中学生でもわかる言葉」で解説しながら、社会や会社の本質を学べる構成になっています。
「13歳から」とあるけれど、大人が読んでも唸る内容です。
理由は、ビジネスの根幹をシンプルに表現しているから。
例えば——
- 利益とは何か
- 社会の課題をどう見つけるか
- アイデアを試す方法
- お金の出入りの管理
- チームで成果を出す方法
これらは就活でも直接役立つ知識です。
「多くの人の役に立つものを作って売る」が近道
本書は、お金持ちになるための近道をこう定義します。
「多くの人の役に立つものを作って、売ること」
就活では、企業が「何のために存在しているのか」を理解することが重要です。
それは単に利益を出すためではなく、社会の課題を解決し、多くの人の生活を良くするため。
面接で「御社のどこに魅力を感じますか?」と聞かれたら、この視点から答えると説得力が増します。
学生Aのエピソード:志望動機が変わった瞬間
Aさん(法学部4年)は、志望動機がいつも抽象的で、「御社の理念に共感しました」の一言で終わっていました。
しかし本書を読んで、「三方良し(売り手よし、買い手よし、世間よし)」という近江商人の理念を知ります。
そこからAさんは、志望企業の事業を「三方良し」で分析。「顧客だけでなく地域や環境にも利益をもたらしている」という具体的な視点を加えることで、面接官から「よく調べていますね」と評価されました。
ビジネスは「事業」と「組織運営」の両輪
本書は、会社経営には2つの側面があると説明します。
- 顧客に商品やサービスを届ける「事業」
- 事業を動かすための「組織運営」
就活では前者(事業内容)ばかりに注目しがちですが、後者(組織の仕組み)も企業を理解する鍵です。組織運営の視点があれば、面接で「どんな働き方をしたいですか?」と聞かれたときも具体的に答えられます。
「わからないときは当事者に聞く」勇気
就活中、企業研究や業界研究で壁にぶつかると、「ネットで調べてもよくわからない」ことが多々あります。本書はそんなとき、こう勧めます。
「わからないときは、当事者に聞いてみる」
OB訪問や説明会で素直に質問することは、勇気が要りますが大きな差になります。
インターネットの情報より、現場の声にはリアルな温度感と事例が詰まっています。
学生Bのエピソード:OB訪問で見えた現実
Bさん(経済学部3年)は、証券会社の仕事内容を調べてもピンと来ませんでした。
そこで本書に背中を押され、大学OBに連絡。「お客様との信頼関係を築くための工夫は何ですか?」と尋ねたところ、具体的なエピソードと数字で答えてくれました。
この経験で、志望動機が一気に現実的になり、ESの通過率も上がりました。
数字や事実で考える習慣
本書は、「グラフや数字など、事実に基づいて考える」重要性も説きます。
就活でも、「なんとなく」で語るより、数字やデータを交えて話すと説得力が増します。
例えば——
「アルバイトで売上を伸ばしました」よりも
「キャンペーンを提案し、売上を前年比15%伸ばしました」の方が印象に残ります。
まとめ——就活は社会を学ぶ最高の実践の場
『13歳からのMBA』は、社会やビジネスの仕組みをやさしく解説しながらも、奥深い問いを投げかけてくれます。
- 企業はなぜ存在するのか
- 利益は何に使われるのか
- 社会の課題をどう見つけ、解決するか
これらを理解すれば、就活は単なる「採用試験」ではなく、社会を知り、自分の役割を見つけるためのプロセスになります。
就活での自己分析や企業研究に迷っているなら、この本を一度手に取ってみてください。
あなたの中に、「ビジネスの地図」が描かれ始めます。