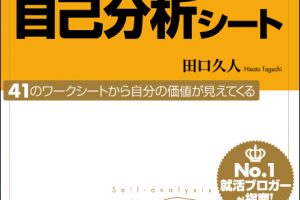「構造化思考」で就活を勝ち抜く——『構造化思考のレッスン』が教えてくれること
頭の中がこんがらがる瞬間
面接の帰り道、ため息をついたことはありませんか。
質問に答えている途中で話があちこち飛び、結局自分でも何を言いたいのかわからなくなる。
面接官の反応もいまひとつで、「またやってしまった…」と肩を落とす。
就活の現場では、こんな場面が繰り返されます。
自己PRを考えていても、ゼミやアルバイト、ボランティア、資格勉強など話題はたくさんあるのに、うまく一本の線につながらない。話せば話すほど、聞き手の頭の中には「?」が浮かんでいくような気がしてしまうのです。
私たちに今、必要なのは——頭の中のごちゃごちゃを整理する力です。
議論を一瞬でまとめる人は何をしているのか
大学のゼミやアルバイト先のミーティングで、こんな人を見たことはありませんか。
みんなが思い思いの意見を出し合っているときに、
「あ、それって要するに〇〇の話ですよね」と一言でまとめる人。
その瞬間、場の空気がスッと整理され、次のステップに進むことができる。
こういう人は、頭の回転が早いだけでなく、情報を構造的に捉える力を持っています。
著者の荒木博行さんは、その典型が「編集者」だと言います。編集者は、膨大な原稿を読み込み、見出しや目次で全体を整理し、さらに凝縮してタイトルに落とし込みます。
つまり、日常的に「構造化」を行っているのです。
『構造化思考のレッスン』という一冊
今回ご紹介する『構造化思考のレッスン』は、この「情報や考えを整理して、相手にわかる形にする力」を体系的に学べる本です。
著者は株式会社学びデザイン代表取締役の荒木博行さん。本の中には「コウゾウ」という四角いロボットのキャラクターが登場し、読者を“構造化思考の世界”へと案内してくれます。
難しそうに聞こえる内容も、このキャラクターのおかげで親しみやすく、テンポよく学べるのです。
就活に直結する「構造化の5P」
本書の最大の特徴は、構造化を5つのステップで整理していることです。
1. Purpose(目的)
なぜ構造化するのか。ゴールを定めなければ整理の方向が定まりません。
就活なら「自分の強みを伝えるため」や「志望動機をわかりやすく説明するため」など。
2. Piece(断片)
具体的な材料を集めます。経験、事例、データなど、細かくリストアップ。
たとえば自己PRなら、アルバイト経験、ゼミ活動、資格取得など。
3. Perspective(視点)
目的と断片をつなぐキーワードを見つけます。
「リーダーシップ」「課題解決」「継続力」など、断片をひとつのテーマにまとめる軸です。
4. Pillar(支柱)
視点に沿って断片をグルーピングし、整理します。
少なければ少ないほど、全体像がすっきりします。
5. Presentation(表現)
整理した内容を、最もわかりやすい形で提示します。文章、図解、口頭説明など、相手や場面に応じた見せ方を選びます。
学生Aのエピソード:混乱から脱出できた瞬間
Aさん(経済学部4年)は、自己PR作りで壁にぶつかっていました。
ゼミ活動、長期インターン、サークル運営、ボランティア…経験は豊富。
でも、エントリーシートに書こうとすると、話が長くなり、何をアピールしたいのか自分でもわからなくなる。
そんなとき、Aさんは本書の「5P」に沿って整理を始めました。
- Purpose:「企業に対して、自分は課題解決力のある人間だと伝える」
- Piece:「ゼミでのデータ分析経験」「インターンでの業務改善」「サークル予算管理」「ボランティアの運営」
- Perspective:「現状把握 → 課題発見 → 解決策実行」という流れ
- Pillar:「分析力」「実行力」という2本柱
- Presentation:ピラミッド図に整理し、ESに反映
結果、文章はコンパクトになり、面接官にも「話がわかりやすい」と評価されました。
Aさんは「頭の中の霧が晴れた感じがした」と振り返ります。
なぜ順番が大事なのか
多くの人は、この5つのステップのうち、最後の「Presentation」から入ってしまいます。
つまり、見た目やフォーマットを先に考えてしまうのです。
でも、それは地図を描かずに旅に出るようなもの。
途中で道に迷ったり、行き先があやふやになったりします。
荒木さんは、必ず最初から順番に進めることを勧めています。
特に就活では、自己PRや志望動機を「見栄え」だけ整えても、中身が伴わなければ説得力が出ません。
まずは「断片」を出し切る
構造化の第一歩は、とにかく頭の中にある断片を洗い出すことです。
就活準備でいうなら、これまでの経験を細かく書き出すこと。
アルバイトで任された業務、ゼミでの発表、サークルの役割、資格の勉強法、ボランティア活動…なんでも構いません。
この段階では質より量。
荒木さんも「いきなり視点(Perspective)から入るのは難しい」と言います。
まずは材料を出し切ることが大事です。
Pillarを立てると道が見える
断片を出し終えたら、それらをグループに分けます。
この支柱(Pillar)は、少ないほど全体像がすっきりします。
さらに、Pillar同士の関係性は3種類に分類できます。
- 独立関係:それぞれが別のカテゴリ
- 連続関係:順序や流れがある
- 因果関係:原因と結果で結ばれている
自己PRを作るとき、例えば「計画性」「行動力」「継続力」の3つに分けて、それぞれに具体例を当てはめると、話が一気に整理されます。
学生Bのエピソード:GDで存在感を発揮
Bさん(文学部3年)は、グループディスカッションが苦手でした。
発言しても話が脱線し、まとめ役にはなれない。
でも、本書で学んだ図解の技術を使ってみることにしました。討議テーマは「地域の観光客を増やす方法」。
Bさんはホワイトボードに2軸のマトリクスを描き、横軸を「短期/長期」、縦軸を「低コスト/高コスト」に設定。出てきた意見をそれぞれの枠に分類していくと、議論が整理され、優先順位も明確に。
最終的にBさんは「議論を前に進めた人」として評価され、グループ全員から感謝されました。
図解で見える化する力
本書では、ビジネスでよく使われる図解ツールも多数紹介されています。
- フロー図
- 循環図
- ベン図
- ピラミッド図
- マトリクス
- ロジックツリー
これらは就活のあらゆる場面で役立ちます。
特にグループディスカッションや面接で使えば、整理力と論理性を一度にアピールできます。
まとめ——構造化は就活の地図であり武器
就職活動は、限られた時間で自分を正確に、魅力的に伝える戦いです。
そのためには、情報を整理し、わかりやすく構造化する力が欠かせません。
『構造化思考のレッスン』は、その技術を5つのステップに分けて、わかりやすく教えてくれます。構造化思考は、あなたの就活の地図であり、武器です。
面接で迷子になりそうなとき、エントリーシートで言葉がまとまらないとき、この5Pを思い出してください。あなたの話は、必ず相手に届くようになります。
-scaled.jpg)
-150x150.jpg)
-300x200.jpg)