面接もプレゼンも怖くなくなる——『対話するプレゼン』が教える「共創型コミュニケーション」
「発表」のイメージが変わる瞬間
就活のグループディスカッションや最終面接。
「あなたの考えを発表してください」と言われた途端、心臓がバクバク。
原稿を必死に覚えてきたのに、頭が真っ白になり、早口で一気に話し終える——。
終わった後、相手の表情は硬く、質問も少ない。
「ちゃんと伝わらなかった…」そんな自己嫌悪に陥ったことはありませんか。
私も学生時代、まさにこのパターンでした。
でもあるとき、「プレゼン=完璧なスピーチ」ではないと知り、緊張が一気に減ったのです。
そうなりたい人におすすめなのが、岩下宏一さんの『対話するプレゼン』。
「一方的に話す」から「一緒に作る」へ
多くの人は、プレゼンを「事前に全部準備し、当日完璧に発表するもの」と思っています。ですが、本書はその常識をくつがえします。
岩下さんは、プレゼンを「相手と共に作る対話の場」と定義します。つまり、プレゼンのゴールは相手を黙らせることではなく、相手とやりとりしながら“より良い結論”を作っていくこと。
これなら、就活の面接やGDも同じですよね。
聞き手を納得させるより、一緒に納得できる答えにたどり着くほうが、ずっと自然です。
著者の異色すぎる経歴
岩下さんの経歴は一風変わっています。
NTTの人事部で新卒3000人採用を統括し、NTTコミュニケーションズの人事部立ち上げにも関わる——それだけでも十分すごいのに、なんと劇団四季のオーディションに合格し俳優に転身。
演じる力、聴く力、間を取る力。
舞台で培ったこれらのスキルが、プレゼン指導に活かされています。
「伝える」だけでなく「一緒に場を作る」ことの大切さは、舞台もプレゼンも同じだとわかります。
就活に役立つ『対話するプレゼン』のポイント
本書で印象的だったのは、従来のプレゼンの逆を行く発想です。
- 情報を詰め込みすぎない:時間の3分の1は余白に
- ストーリーに固執しない:その場の相手の関心を優先
- 原稿を読み上げない:言葉はその場で作る
- 流暢さより自然さ:言い間違いもOK
- 質疑は最後ではなく冒頭から
この考え方を就活に置き換えると、「完璧な答えを暗記して披露する」より、「相手の質問に耳を傾け、その場で考えて答える」ことが評価される、ということです。
学生Aのエピソード:暗記地獄からの解放
経営学部のAさんは、面接での自己PRが苦手でした。
文章を丸暗記し、本番で暗唱するスタイル。
でも、面接官の表情は硬く、「質問はありますか?」と聞かれると沈黙…。
Aさんは本書の「半生話法」を試すことにしました。
これは、話す内容を完全暗記せず、要点だけ覚え、あとはその場で言葉を作る方法です。
次の面接では、面接官の頷きや質問に合わせて話を変えたところ、会話が弾み、笑顔も増えました。
「完璧に覚えて話す必要なんてなかった」と気づいた瞬間でした。
空気作りの7つのアプローチ
岩下さんは、プレゼンは始まる前から勝負が始まっていると言います。
本書にある「空気作りの7つのアプローチ」は、就活でもすぐに使えます。
- 感謝を伝える
- 名前の読み方を確認する
- 気づいたことを褒める
- 話しやすい話題を出す
- 終了時刻を確認する
- 資料は空気作りが終わってから配布
- 本題の最初に「目的地」と「道のり」を示す
面接の冒頭でこの流れを意識するだけで、会場の空気は柔らかくなり、話しやすくなります。
学生Bのエピソード:GDで初めてリーダーになれた日
文学部のBさんは、グループディスカッションが苦手。
意見を言っても流され、存在感を出せませんでした。
本書で学んだ「冒頭から質疑を行う」を応用し、GDの最初に他のメンバーへ「今日はどんな方向でまとめたいですか?」と質問。
これで全員の意見を引き出し、その後の議論を整理する役割を自然に担うことができました。結果、ファシリテーターとしてチームから感謝され、評価も高まりました。
「対話型」なら緊張しない理由
従来のプレゼンは「0か100かの審判を仰ぐ場」となりがちです。
ですが、岩下さんが提案するのは「用意したストーリーを叩き台にして活発な話し合いを行う場」。この発想に変えると、失敗の恐怖が薄れます。
なぜなら、話し合いは「間違えてはいけない」ものではなく、「より良くするために意見を出す場」だからです。
就活で使える「問題解決ストーリー」
本書では、プレゼンを「より良い未来の実現を予感させる物語」と定義しています。問題解決の流れは以下の4ステップ。
- 背景の確認
- 問題の特定
- 原因の特定
- 解決策の決定
この流れは、自己PRや志望動機にもそのまま使えます。例えば「過去に直面した課題」を、上記の順で説明すると、聞き手は自然と納得してくれます。
まとめ——就活は「発表」より「共創」
就職活動の面接やGDで求められているのは、完璧なスピーチではありません。
大事なのは、相手とやりとりしながら、その場で価値を生み出すこと。
『対話するプレゼン』は、そのための具体的な方法を教えてくれます。
「話す」から「一緒に作る」へ——この意識の転換が、就活を変えます。
緊張しがちなあなたこそ、この本のメソッドが味方になります。
-scaled.jpg)
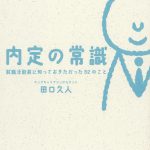
-150x150.jpg)
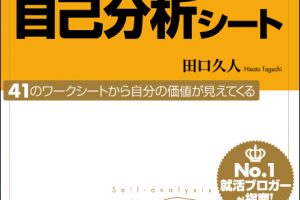
-300x200.jpg)





