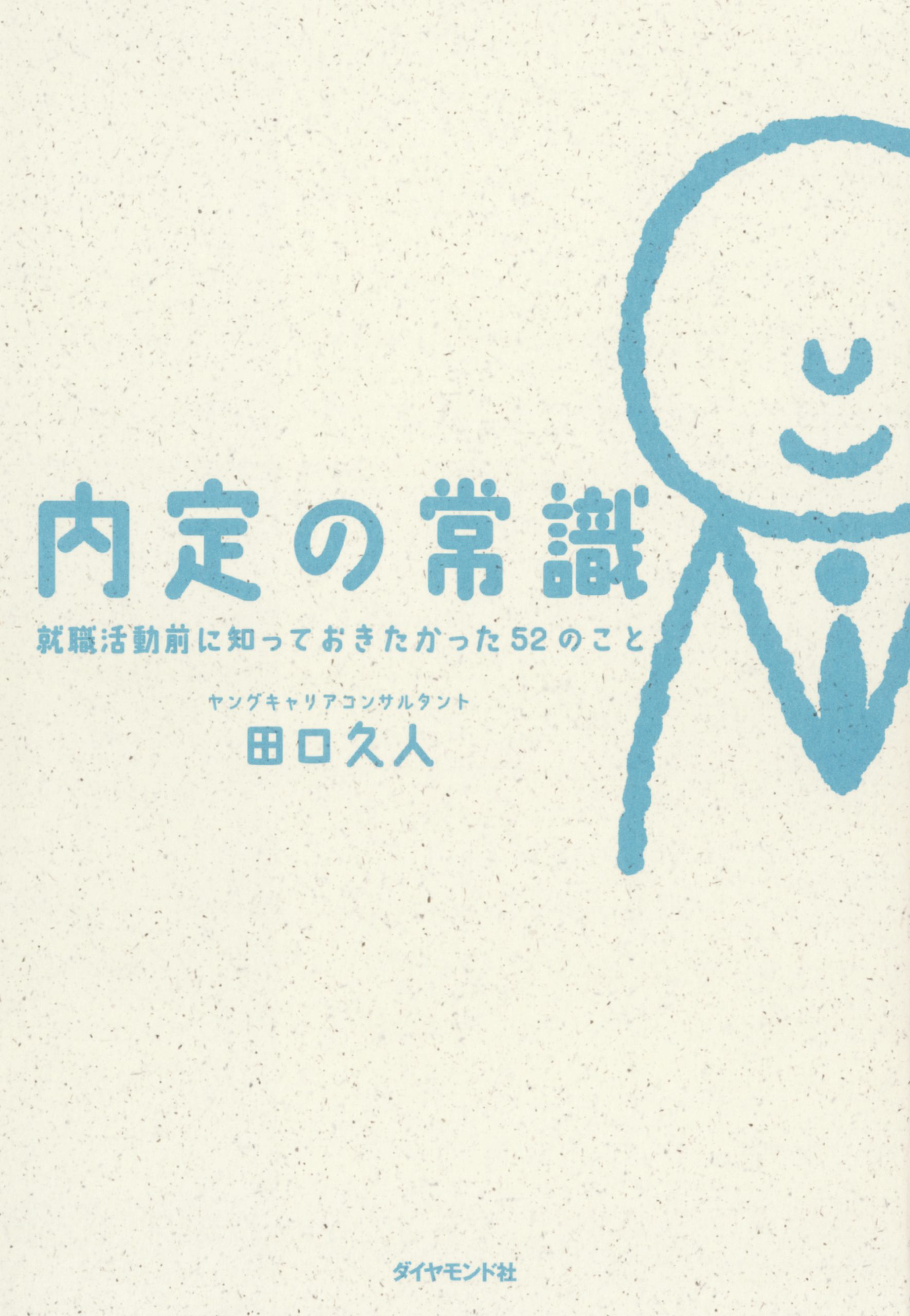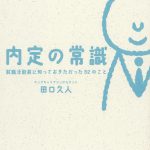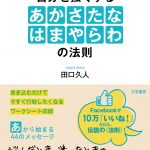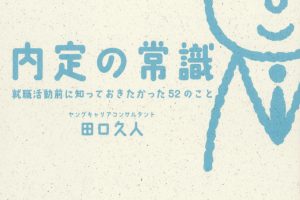「同じ業界でも、こんなに違うの?」
ページをめくった瞬間、私は目を疑いました。
上場企業404社をビジネスモデルの視点から分析した『会社四季報 業界地図』ビジネスモデル版。
そこには、企業の稼ぎ方と財務体質の関係が、克明に描かれていました。
中でも印象的だったのは、ビジネスモデルの違いによって、平均年収に400万円近い差が生じているという事実。同じ日本で働きながら、ここまでの差があるのです。
背景:9つのビジネスモデル
本書では、企業を次の9つのビジネスモデルに分類しています。
- 製造販売モデル
- 流通小売モデル
- 合算モデル
- 継続モデル
- フリーミアムモデル
- 設置ベースモデル
- 広告モデル
- マッチングモデル
- 補完財プラットフォームモデル
企業によっては複数のモデルを組み合わせていることもあります。
この分類を使うと、業績の特徴や将来性が驚くほど見えやすくなるのです。
展開:モデルによる差は歴然
例えば、高収益で知られる「補完財プラットフォームモデル」。
任天堂やソニーグループがこの代表例です。
対照的に、食品や日用品を中心に扱う「合算モデル」(ウエルシアHD、イオンなど)と比べると――平均年収で約400万円の差。
営業利益率で見ても差は歴然。
- 合算モデルのトップ:オリエンタルランド 26.7%
- 補完財プラットフォームモデルのトップ:任天堂 31.6%
- そして驚きの記録――継続モデルのトップ、インテグラルは 78.1%。
数字は、ビジネスモデルが持つ力を雄弁に物語っています。
事例1:アスクルの販売システム
アスクルは、自社の営業所を設けず、全国の文具店などを販売代理店(エージェント)として活用。
この発想は、物流や営業の固定費を大幅に削減するだけでなく、代理店の営業力や顧客ネットワークをそのまま取り込むという利点があります。
代理店は仕入れや在庫管理、配送をせずに顧客サポートに専念できますから、双方にとって効率的です。
結果、アスクルは多品種の商品を短時間・低コストで届ける仕組みを構築。
代理店は地域密着の強みを発揮し、アスクルは全国規模でブランドを広げる――まさに**「Win-Winのモデル」**です。
事例2:合算モデルのカラクリ
合算モデルの鍵は、低価格なフック商品と利益率の高い商品の合わせ売り。
ドラッグストア最大手・ウエルシアHDを例に見てみましょう。
売上構成では食品が22.6%とトップですが、粗利益では医薬品(25.5%)や化粧品(17.1%)に劣ります。
つまり、食品は「集客のためのフック」であり、利益は医薬品や化粧品で稼ぐ仕組み。
お客さんが牛乳やパンを買いに来たついでに、化粧水やサプリメントを手に取る――これこそが合算モデルの強みです。
この発想はスーパーやコンビニにも応用可能で、商品構成を変えるだけで収益構造を一変させられます。
事例3:マクドナルドの稼ぎ方
日本マクドナルドHDは、ハンバーガーの販売よりも、継続モデルであるフランチャイズ事業が稼ぎ頭。
国内2982店舗のうち、自社運営は約3割(878店)、残りの2104店はFC店舗です。
フランチャイズ店舗は、ブランド使用料や売上の一部を本部に支払います。
この収益は、店舗が増えるほど安定して積み上がるストック型収入となります。
つまり、マクドナルドは**「店舗という資産を持つより、店舗網という仕組みを売る」**ことで高収益を実現しているのです。
事例4:フリーミアムの巧妙さ
チャットワークを提供する**kubell(クベル)**は、無料プランと有料プランを併用するフリーミアムモデルの代表例。
登録IDは約740万、そのうち有料契約は80万。
無料ユーザーは直接の収益源ではありませんが、サービス価値を広める存在として重要です。
また、無料で使ってもらうことで顧客の業務に組み込み、後から有料化へと移行させやすくなります。
このモデルはクラウドサービスやゲームアプリにも多く採用され、**「使ってもらう→手放せなくする→課金へ」**という心理的な流れを作ります。
事例5:マッチングモデルの高収益
中古車オークションの**ユー・エス・エス(USS)**は、営業利益率50.1%を誇ります。
在庫を持たず、取引の場と仕組みを提供し、その手数料で稼ぐ。
この仕組みは、景気変動の影響を受けにくく、需要が安定しています。
また、取引の回数が増えるほど利益も拡大するため、スケールメリットが大きいのも特徴です。
この構造は、不動産仲介、求人サイト、旅行予約サイトなど、多くの業種で応用されています。
事例6:構築が難しい補完財プラットフォーム
補完財プラットフォームモデルは、そもそも採用している企業が少数。
構築には膨大な初期投資と時間がかかりますが、一度顧客基盤を築けば極めて強力です。
任天堂のゲーム機とソフトの関係はその典型。
ハードを売ることでユーザーを囲い込み、ソフトや周辺機器で長期的に収益を得る仕組みです。
さらに、ソフト開発者にとっても任天堂のプラットフォームは魅力的な市場であり、自然とエコシステムが育ちます。
このように「本体+周辺コンテンツ」での収益モデルは、長期的なブランド力と価格決定力を生みます。
転機:ランキングが教えてくれる未来
本書第4章「ランキングで見る 9つのビジネスモデルの実力」では、営業利益率ベスト10が紹介されています。
継続モデルのトップ10を見ると――
1位 インテグラル 78.1%
2位 日本取引所グループ 57.2%
3位 オービックビジネスコンサルタント 44.7%
…と、安定かつ高収益な企業がずらり。
このランキングを見るだけで、将来有望な企業の姿が浮かび上がるのです。
数字は嘘をつきません。むしろ、未来を映し出すレンズになります。
学び:ビジネスモデルは「戦い方」
本書を通じて痛感するのは、ビジネスモデルは単なる経営手法ではないということ。
それは、企業の運命を左右する「戦い方」そのものです。
同じ商品を売っていても、モデルが違えば利益率も年収も大きく変わります。
投資家にとっては投資判断の材料になり、起業家にとっては勝ち筋を見つける地図になります。
私たちの日常業務にも、この視点は応用できます。
提案書の作り方、営業の優先順位、顧客との関係構築――全て「どう稼ぐか」という戦略に直結しているからです。
まとめ:あなたの仕事も「モデル」で変わる
私たちはつい、「どの商品が売れているか」「どの企業が話題か」に目を奪われがちです。
しかし、その裏にある稼ぎ方の仕組みを見抜ければ、ビジネスの景色は一変します。
もし今の仕事が伸び悩んでいるなら――商品やサービスそのものよりも、ビジネスモデルの設計を見直すことが、最大の突破口になるかもしれません。
404社のデータは、私たちにこう教えてくれます。
「勝ち続ける会社は、売り方ではなく稼ぎ方を磨いている」